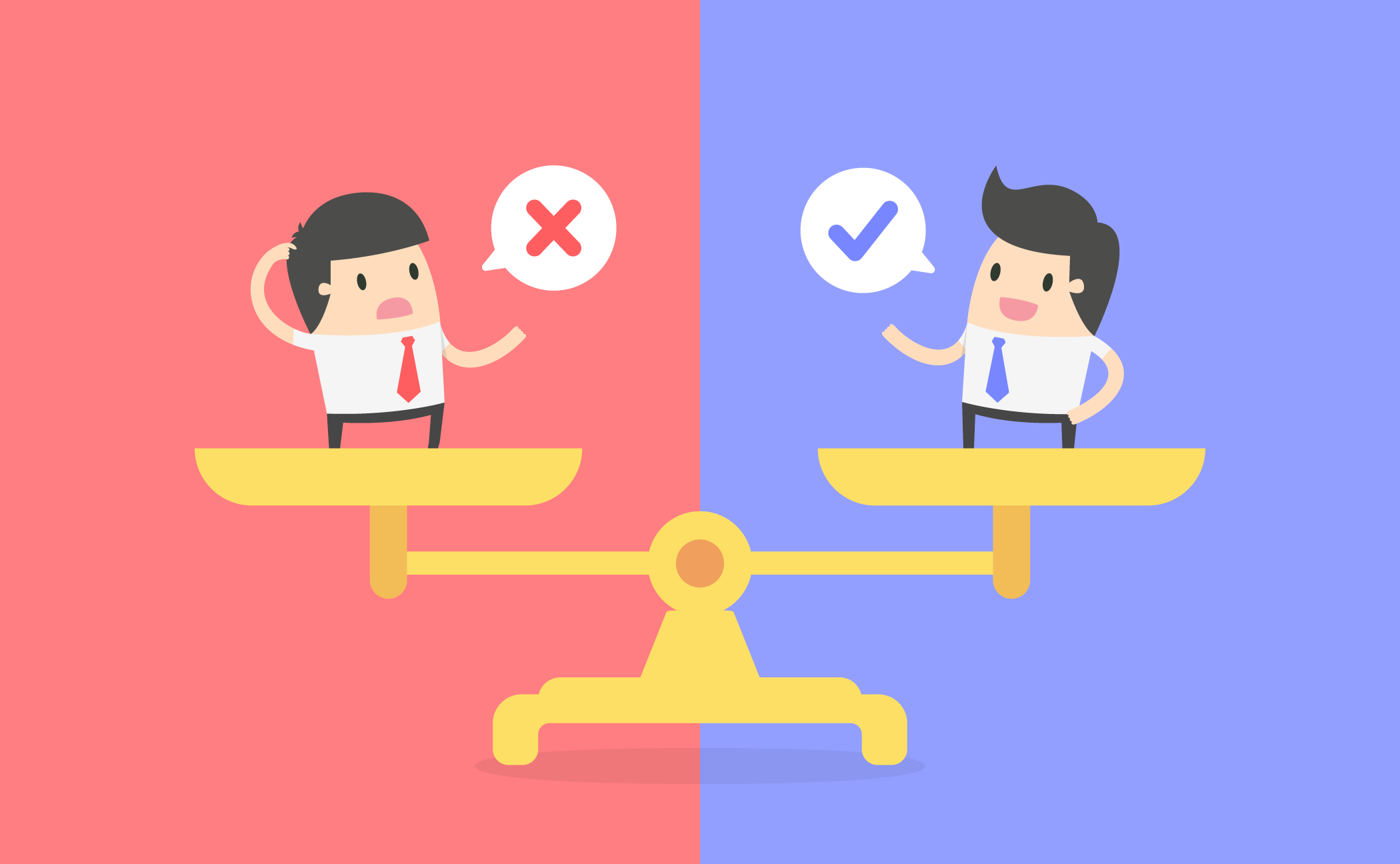内製と外注のどちらを選ぶかは企業にとって重要な決断です。両者にはそれぞれメリットとデメリットがあり、適切な選択をすることでプロジェクトの成功に繋がります。ここでは、内製と外注の比較を通じて、カタログ制作で失敗しないための選択をガイドします。
社内でカタログを制作するメリット・デメリット
内製のメリットとは
自社の製品の特徴、ターゲット層、競合との違いについて熟知していること、社内リソースがあることでしょう。具体的には、
社内での直接やり取りで進んでいくため、迅速な意思決定や情報の反映が可能です。業務が進む過程での修正や意見のフィードバックもスムーズに行えます。
発売前の製品情報や営業情報、個人情報などの秘密情報について、外部に出さずに済みます。外部の製作会社に制作を依頼する場合は、情報を開示する前に秘密保持契約(NDA)を締結するのが一般的です。
デザイン、コピーライティング、DTP、マーケティング担当者が社内にいる場合、その人員を活用することで制作に必要なコストを最小限にすることができます。但しその場合、内製化によって生じる社員の業務負荷や、専門的な制作スキルの取得が必要になることも考慮すべきです。
などが挙げられます。
内製のデメリットとは
内製の場合、やはり担当する社員の業務負荷と、やはり社内の視点だけに偏りがちになり、客観的な評価を得にくいというデメリットもあります。具体的には
カタログ制作は多くのステップを含み、企画、デザイン、組版、校正など手間がかかります。特に、普段の業務が忙しい中での制作となると、自社社員の負担がどんどん大きくなり、他の業務に影響を及ぼす可能性があります。
内製の場合、業務がどうしても属人化し、その担当社員がいないとわからない、進められないといった、いわゆる「ブラックボックス化」になってしまうケースが多々あります。組織としての管理ができない状態になることで、トラブルやミスの顕在化とその対処が遅れてしまうといったことが起こります。また社内業務であることから、スケジュールの遅延が発生しやすくなります。
制作の専門的な知識が足りないと、カタログのクオリティが大きく損なわれる可能性があります。デザインにおいては配色やレイアウトのバランス、コピーライティングは、的確かつ魅力的な言葉とターゲットに響くメッセージが必要です。また、DTP組版においても経験が少ないうちはオペレーションミスや校正ミスが発生し、間違った情報のまま印刷されてしまうことも起こります。これらの全ての要素が十分でないと、結果的にターゲットユーザーの目を引くことができなくなり、販売機会の損失につながります。
などが挙げられます。
外部の制作会社にカタログを依頼するメリット・デメリット
外注のメリットとは
外部に発注するメリットは、カタログ制作の専門家が全ての制作プロセスを受け持つことで、社内スタッフが本来の業務に集中できます。具体的には
カタログと一口に言っても、使う目的やターゲットによって見せ方が異なります。外部の制作会社は、多くの企業やさまざまな業種のカタログを手掛けているため、多様な視点やアイデアを持っています。社内で考えつかない新しいデザインやコンテンツの提案、顧客の心をつかむ工夫を盛り込んだ内容を提供してくれます。
外部の制作会社は複数のプロジェクトを同時に進行できる体制を持っていることが多く、大規模なカタログ制作や、急な納期にも対応できる柔軟性があります。例えば社内リソースが限られている場合でも、必要に応じて対応を拡大してくれます。プロジェクト管理や納期調整がしっかりしてしていて、安定した進行ができる会社に発注しましょう。
自社での制作に比べ、外部に依頼することで社内の人材や時間を他の重要な業務に集中できます。社内スタッフは、ブランドづくりから誌面に載せる商品内容の選定、販売戦略に力を入れることができます。
などが挙げられます。
外注のデメリットとは
発注側と制作会社が良いパートナーシップを築けない場合は、問題になります。例えば制作に必要に情報を伝えきれてないことで、必然的にやり直しや手戻りが多くなり、イメージとずれたカタログが出来上がるリスクがあります。
制作会社によって見積費用にかなり違いがあります。また、修正段階でレイアウト変更や校正回数が増えた場合、契約外の作業が派生した場合などは追加料金が発生します。これにより、当初の見積の予算より増えることがあるため、慎重なコスト管理が必要です。
外部の制作会社と社内でコミュニケーションがうまく取れないと、情報の伝達ミスや意図の違いから、希望通りの結果が得られないことがあります。特に、プロジェクトが進行する中で修正内容等のフィードバックの反映が遅れると、納期の遅れや品質の低下が起こる可能性があります。
まとめ
コストを抑えたいのは、どの企業も同じです。内製と外注のどちらかを選ぶ際の費用対効果を考えるポイントをまとめました。カタログの規模、制作期間、スタッフのマンパワー、見えるコスト、隠れたコストなどを考慮して、内製と外注のどちらが最適かを判断することが重要です。
| ポイント | 内製 | 外注 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 社内リソースを活用することで初期コストはかからないが、隠れたコスト(ツール、ソフトウェア、時間)が発生する場合がある。 | デザイン、DTP組版、管理、印刷など初期費用がかかる。カタログの仕様や要望を詳しく伝えること金額がより明確になる。 |
| 長期的なコスト | スキルアップのための教育コスト、ソフトウェアの更新費用、人権費などが長期的に発生する。 | 継続的なカタログの場合は、2冊目以降、制作方法の工夫やスキルで長期的にコストを抑えやすい。 |
| クオリティと専門性 | 社内に十分なスキルがない場合、高い効果を得られず、社内コストに見合わない結果になるリスクもある。 | プロフェッショナルならではの専門スキルで、デザインも、組版もミスのない制作方法でコストに見合った効果が得られる。 |
| 時間対効果 | 制作時間が長引くことや他の業務とのバランスが崩れたり、時間的な制約が発生する場合がある。 | 社内リソースを他の業務に集中させることができる。短期的に迅速にプロジェクトを進められる |
| 進捗管理・納期 | プロジェクトの方向性をその都度変更できたり、社内調整が容易。変更が多くなったり、本来業務を重ねると納期が遅れがちになる。 | 決められた納期から制作スケジュールを立てる。作業量が増えた場合でも、作業人員の増加など、柔軟な対応ができる。 |